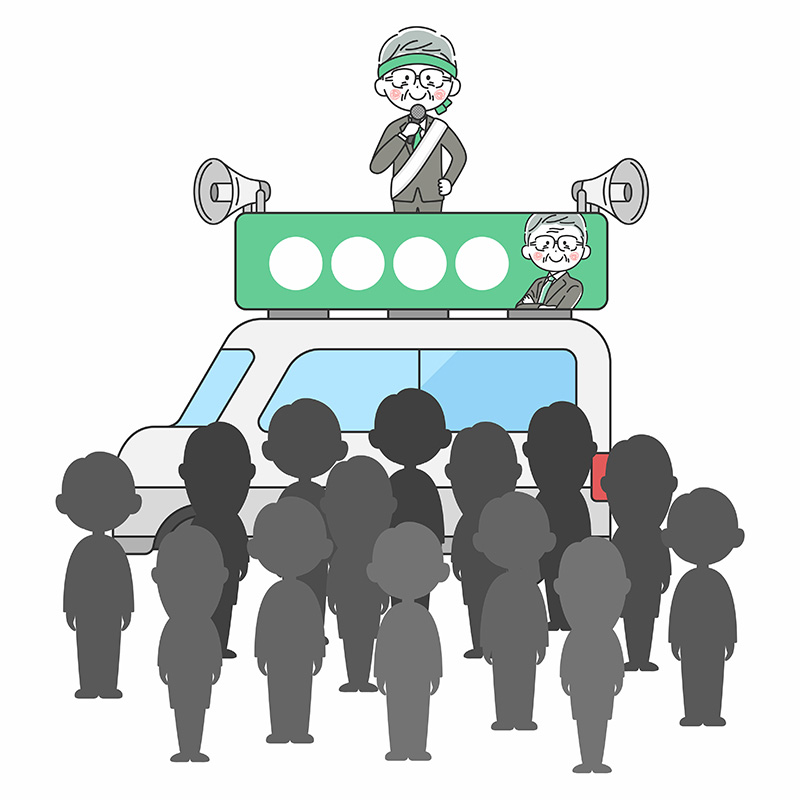どんな話?
弘南バスとその労働組合は、昭和34年3月10日~25日にかけて結んだ労働協約で、会社の繁栄と事業計画達成のため、協約の有効期限である昭和35年6月7日までは仲良く平和的にしましょうと取り決めました。
ところが労働組合側は、期限前の昭和35年3月7日~5月4日にかけて、期間満了後の労働協約改訂と賃上げを求めてストライキを実施。しかもその際、社内に大量のビラを貼ったり、会社の許可を得ずに職場集会をしたり、控室で労働歌を大声で歌ったりと、会社から見たら業務妨害としか思えないような行為を行いました。
怒った会社は、「会社の秩序を壊した」として、組合の支部長と副支部長を懲戒解雇。組合側は懲戒解雇は無効だとして、裁判を起こしました。
争点
会社側は、「昭和34年に結んだ労働協約で、問題は平和的に解決すると取り決めしたではないか。さらに昭和35年6月7日まではこの労働協約は有効だから、有効期間内にこんなことをされても困る。」と主張、協約違反により会社の秩序を乱したので、解雇は正当だとしました。
1、2審とも会社側が敗訴して、最高裁に上告しました。
判決は?
仮に組合の行ったことが、会社と結んだ労働協約の「平和義務」に違反してストライキをしたとしても、それは法律違反なのではなく、私人間の契約を守らなかっただけに過ぎない。そのストライキに加わった一組合員も同じことだから、ストライキをしたからといって、懲戒解雇にすることは出来ませんと判断し、会社の上告を棄却しました。
いのしし社労士の解説
この判例を読んでも、ぴんと来ない方も多いかと思います。悪いのは約束を守らず大騒ぎした組合じゃないかと。
しかしそうではないのです。
民間の主な労働組合がストライキをしなくなって久しく、労働組合の組織率も20%を割り込む現状では、「労働組合法」という法律に馴染みがなくても致し方ないところ。
キモの部分をかいつまんで説明してみましょう。
(1)労働者は、対等に使用者と交渉できるようにするため、労働組合を組織することができる。
(2)労働組合は暴力の行使などを除けば、正当な活動には刑法の規定により、処罰されない。
(3)「不当労働行為」と呼ばれる会社がしてはならない行為(組合活動での解雇など)がある。
(4)適法に行われたストライキなどの行為で会社が損害を受けても、賠償請求ができない。
(5)労働組合と会社は「労働協約」と呼ばれる、労働基準法よりも就業規則よりも強い決まり事を結ぶことが出来る。
さて、判例を労働組合法に当てはめてみましょう。
(1)労働組合が期限後の労働協約について、期限前に交渉したり、ストライキなどを行うことは、ある意味当たり前のこと。
(2)法的に問題がない行為で社員をクビにした会社側の行為は、「不当労働行為」となり、労働組合法上の違法行為となり、無効。
(3)ただし、労使で合意した労働協約の平和義務には違反しているとすれば、その範囲において組合側に責任が生じる。
となります。
もちろんストライキなどの決定的な状況に至る前に、会社と組合が誠実に交渉して、合意することが望ましいのは言うまでもありません。
しかし、不幸にして争議行為に至ってしまった場合であっても、労働協約などで、可能な限り平和的で静穏にストライキを行うように合意しておくことで、冷静な交渉が出来る環境を整えることが大切ではないでしょうか。
関係条文
労働組合法、憲法第28条(労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権)、刑法第35条(正当行為)
学説など
平和義務の根拠について、3つの学説があります。
(1)内在説・・・労働協約は労使合意に基づき締結される制度であり、本質的に平和義務が内在しているという説。
(2)意思説・・・対立した内容について、当面の間妥結したに過ぎず、労働協約を締結した労使双方の意思に基づくものとする説。
(3)信義則説・・・契約法理を適用し、締結当事者間の信義則を根拠とする説。
出典
「別冊ジュリスト労働判例百選」