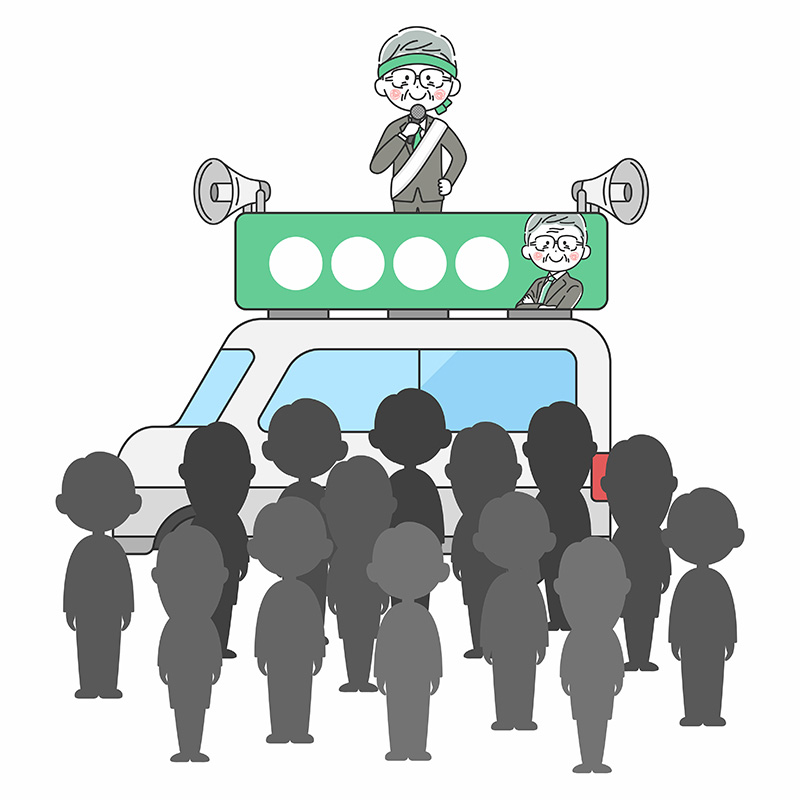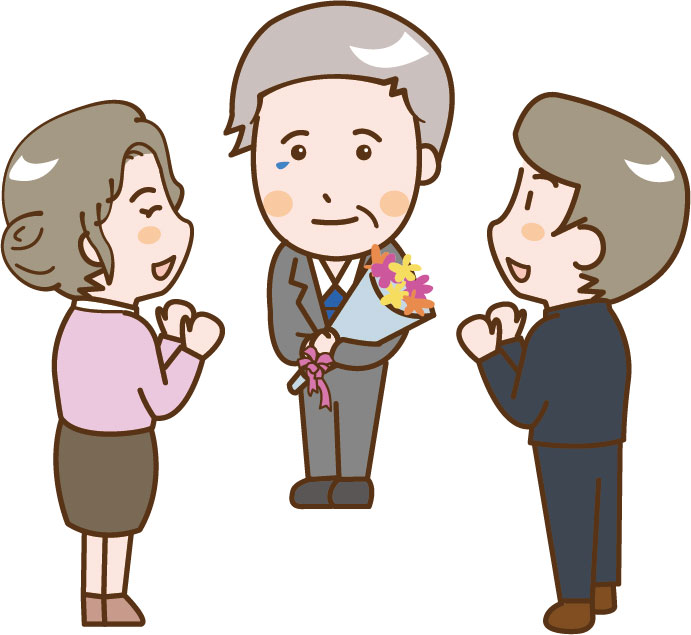西日本鉄道事件ってどんな話?
西日本鉄道株式会社は、バス等の運転手による運賃のネコババを防ごうと、就業規則で「所持品検査」の項目をつくり、随時、検査を行ってきました。
ところが検査する人によって、検査方法がまちまちだったので、労働組合と話し合って一斉に行うことにしました。組合側としても、個人の人権尊重や検査する人の教育徹底などを条件に、一斉検査を認めて、組合の機関紙で周知をしました。
ところが昭和35年3月11日に行われた所持品検査で、乗務員の一人、Aさんは「帽子やポケットの中まではいいけれども、靴を脱がせてまで調べるのは、自分は承諾しない」と言い張って、結局靴を脱ぎませんでした。
この行為を重く見た西鉄は、Aさんを「会社の指示に従わず、職場の秩序を乱した」として、出勤停止のあと労使協議の上、懲戒解雇としました。Aさんは懲戒解雇は行き過ぎだとして、裁判を起こしました。
西日本鉄道事件の争点
靴を脱いでまで所持品検査をする必要があったのか、その検査は人権侵害にあたらないのか、また靴を脱ぐ検査を拒んだ行為が「職場秩序の混乱」に当たるのか、仮に会社側の主張が正しいとしても、懲戒解雇は行き過ぎではないのか、などが争点となりました。
解雇無効の仮処分については、検査そのものは有効だが解雇は無効、第一審は仮処分を取り消して解雇を有効、第二審もAさんの控訴棄却となりました。
西日本鉄道事件の判決は?
最高裁は、所持品検査はその性質上つねに人権侵害のおそれがあるため、4つの要件を課しました。
(1)検査を行う合理的理由があること、(2)検査の方法や程度が一般的に妥当であること、(3)制度として画一的に実施されること、(4)就業規則などで検査の根拠を明示すること、その上で、この事件については、4要件を満たしており、Aさんが会社の指示を拒否する特別な理由は見出しがたく、処分の経緯や情状などを考慮しても、解雇は妥当と判断し、上告を棄却しました。
いのしし社労士の解説
現金を多く取り扱う職場では、従業員の横領リスクが他の職場よりも高く、例えば銀行の内部監査は相当厳しいですし、郵便も郵政監察官制度が生きていて、郵便局員の業務上横領などに目を光らせています。昔、旧国鉄でたばこ銭数百円を着服したとして、懲戒免職になった人もいたくらいですから、金銭の管理が、一定厳しいのも当然と言えます。
個人的には、この判例の「検査拒否」での懲戒解雇は厳しすぎるとは思いますが、ある程度の懲戒処分はやむを得ないのではないでしょうか。ただ人権と所持品検査の関係は、判例や学説でもとても重要視されていて、上記4要件をクリアしていなければ、所持品検査を拒否しての懲戒解雇は違法、とする判例も数多くだされています。
例えば身体検査で裸にするとか、身体を触っての検査、個人の思想信条を侵害するような検査は、法的には事実上不可能と認識すべきでしょう。まずはその必要性を十分に吟味した上で、就業規則にしっかりと位置付けし、従業員の理解を得てから行うことが望ましいと思います。
関係条文
労働基準法第10章(就業規則)第89条~93条、憲法第19条(思想及び良心の自由)、第21条(集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護)
学説など
多数学説は、所持品検査は適法で、検査拒否による懲戒処分は妥当だが、懲戒解雇は許されないとするもの。また一つの傾向として、所持品検査の4要件を厳格に解釈し、所持品検査そのものを違法とする下級裁判例も出ている。「臨時工の手提袋の中」、「作業後の身体検査(引越し作業員)」、「不正取得が疑われる客観的行為がないのに通勤用自家用車内を検査した」、「単なる会社側の見込みだけによる所持品検査」が4要件に反しているとして違法、とされた判例もある。
出典
「別冊ジュリスト労働判例百選」